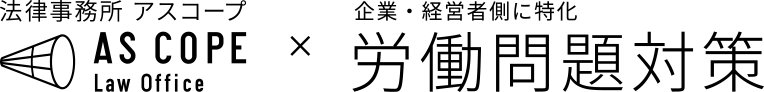復職の可否に関する最近の裁判例の動向

目次
昨今、労使紛争の話題として、従業員のメンタルヘルス問題が取り上げられることが多くなっています。 本NewsLetterでは、今般、関心が高まりつつあるメンタルヘルスの不調を抱える従業員対応について、特に判断が難しい、復職の可否≒自然退職の可否に関する諸問題について、最近の裁判例を基にご紹介させていただきます。
第1 メンタルヘルス従業員対応に関する問題の所在
企業が私傷病による(注1)メンタルヘルスに不調を抱える従業員に対応する際の流れをおさらいすると、①従業員のメンタルヘルス不調に関する申告(診断書の提出)、②休職命令の発令、③休職期間満了による自然退職又は復職(配置転換含む)の判断、という流れになることが一般的です(注2)。そして、この流れの中で、特に③は、従業員の法的地位を決定付けることになるため、企業側の判断に困難を来す場合が多く見受けられます。 復職の可否に関する判断は、様々な要素を総合的に考慮して行われますが(注3)、特に重要視されるのは、主治医等の専門医による休職要因となった精神疾患の「治ゆ」≒「復職可能」に関する診断結果です。しかし、主治医が「復職可能」と診断していても、産業医は「復職不可」と診断するなどして判断が異なっている場合があり、企業側からしてみると、従業員を復職させて良いか、判断に迷う場合があります。 本NewsLetterでは、このような場合に、企業としてどのような事情を考慮し、どのように対応すべきか、について参考としていただくために同種事案に関する裁判例の動向をお示しすることを目的としています。
第2 東京地判令和5年4月10日・労判1324号7頁(ホープネット事件)
1.事案の概要
双極性感情障害を理由に被告企業を長期休職していた原告が就業規則に基づく休職期間満了をもって自然退職扱いとされたことに対し、被告企業に地位確認・未払賃金・慰謝料等を請求した事案です。
2.主たる争点のポイント
復職の可否(「休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復」したといえるか) ・原告は主治医の診断に基づき、労務軽減措置付きでの復職の可能性を主張 ・被告は主に産業医の診断に基づき、復職が不可能と判断 なお、裁判例では、上記争点以外にも、①傷病の業務起因性(本件傷病が業務上の事由に起因する疾病であるか)、②代替業務による復職の可能性(元の業務以外の業務で復職することは可能であったか)、③不法行為の正否(本件退職措置等の対応が不法行為を構成するか)が争点となっていますが、本NewsLetterでは、復職の可否に関する争点に焦点を当ててご紹介します。
3.裁判所の判断(争点2について)
裁判所は、原告の復職可否の判断に当たり、次のように述べて、主治医の復職可能との診断結果を採用せず、産業医による復職不可能との判断を採用し、被告企業による自然退職の取り扱いを有効と判断しました。(以下、引用部分における下線部は筆者による。) 「以上の諸事情を総合すると、延長後の休職期間が満了する令和2年3月時点において、原告が復職に向けた意欲を有しており、また、主治医のC医師からも同月から復職可能である旨の診断がされていたとしても、原告の精神疾患は、平成26年3月以降、6年間余りの長期間にわたって要治療の状態にあり、令和2年3月当時も薬効の強い薬剤が多種類投与されているなど治療が継続されていたものといえ、一方で、原告については休職に入った平成30年9月以降の1年6か月余りの期間、ほとんど外出しないまま自宅療養を続け、その間、復職に向けた生活リズムの改善や外出訓練といった復職に向けた取組は一切図られないままであったことが認められる。そうすると、原告の本件傷病について、令和2年3月時点で復職可能な程度に回復しており、あるいは、復職後ほどなく回復する見込みがあるとは診断し難いとしたD医師の判断は、同時点までの原告の行動等や診療経過とも整合するものとして合理性を有するといえ、かかる判断に本件傷病の病態及び治療に関する一般的な医学的知見も併せれば、令和2年3月時点で原告の本件傷病がC医師の診断のとおり医学的にみて一時的に寛解の状態にあったと解したとしても、延長後の休職期間が満了する令和2年3月末日の時点において、原告が休職前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復していたことはもとより、復職後ほどなく上記の健康状態に回復することが見込まれる状態にあったとは認め難いものといわざるを得ない。」
4.本裁判例の意義
本裁判例は、原告における治療状況(投薬状況)、日常生活の状況といった具体的状態を勘案し、対立する主治医の診断結果を採用するのではなく、産業医による面談評価・労務提供能力の総合判断に基づく復職不可との診断結果の合理性を認め、その診断結果に基づいて行われた自然退職が有効と判断された点に意義があります。
5.留意すべきポイント
(1)裁判例の傾向 主治医の診断結果それのみをもって復職の可否が判断されないのと同様に、産業医の診断結果についてもそれのみをもって復職の可否が判断されるわけではない点は留意する必要があります。 ただし、主治医の診断結果については、裁判例上、「一般的に、主治医の診断は、患者本人の自己申告に基づく診断とならざるを得ないという限界がある」(東京地判平成29年11月30日・労判1189号67頁(東京電力パワーグリッド事件))、「主治医は患者の治療を任務としており、患者の職場の実情には通じておらず、復職した場合に債務の本旨に従った労務提供が可能なのか、復職のため職場においていかなる配慮が必要なのかといった観点からの検討はしない立場にあり、復職可能との主治医の診断書の存在をもって就業可能との立証がされたとはいえない。」(東京地判令和6年5月28日・労経速2568号24頁)と判断された事例もあり、裁判所は、一般論として、主治医の診断結果を必ずしも重視していないように見受けられます。
(2)会社における対応策 裁判例では、復職の可否に関する判断材料として「リワークプログラム」(精神科医の指導の下、臨床心理士が患者本人のリワークへの取組みを一定期間継続的に観察した上で客観的な指標で評価して精神科医に共有し、精神科医が診断を下す内容のもの)を取り入れることに言及したものがあり、主治医による就労可能との見解について、「リワークプログラムの評価シートを参照しておらず、リワークプログラムに関与した医師の見解等を踏まえていないものである上、患者の職場適合性を検討する場合には、職場における人事的な判断を尊重する旨述べていること等の内容自体に照らし、必ずしも職場の実情や従前の原告の職場での勤務状況を考慮した上での判断ではない」などと認定し、同見解を参酌することは相当でないとしています(前掲・東京電力パワーグリッド事件)。 このような裁判例からすると、復職の可否に迷った場合は、このような「リワークプログラム」を行って判断することにより、主治医の判断よりも高い信用度が認められる可能性があります。 また、当然ながら、主治医と異なる立場(会社の職場環境を把握する立場)から診断を行う産業医面談は有用ですし、復職≒休職前に従事していた通常の業務を遂行できるということを意味しますので、実際に休職前の業務に就業可能かどうか、軽減業務ではどうかを休職期間中に試すという方法も有用であると考えられます。