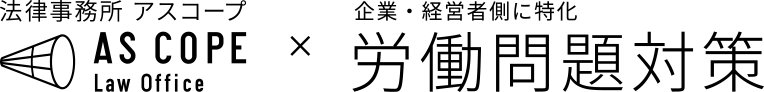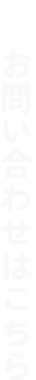社員の退職トラブルを防ぐ!弁護士が解説する「引継ぎ義務」と実務対応 等

Q
退職を申し出てきた社員から、「最終出社日までの残りの営業日は、すべて有給休暇を消化します」と一方的に告げられました。後任者への業務の引継ぎが全くできておらず、このままでは業務に大きな支障が出てしまいます。会社として業務命令を出して引継ぎを強制したり、有給休暇の取得を拒否したりすることは法的に可能なのでしょうか。また、貸与したノートパソコンや制服の返却についても曖昧な態度で、非常に困っています。
退職を申し出てきた社員から、「最終出社日までの残りの営業日は、すべて有給休暇を消化します」と一方的に告げられました。後任者への業務の引継ぎが全くできておらず、このままでは業務に大きな支障が出てしまいます。会社として業務命令を出して引継ぎを強制したり、有給休暇の取得を拒否したりすることは法的に可能なのでしょうか。また、貸与したノートパソコンや制服の返却についても曖昧な態度で、非常に困っています。
労働契約上の信義則に基づき、退職する社員には一定の「引継ぎ義務」があります。しかし、会社が一方的に出社を事実上強制したり、損害賠償を請求したりすることのハードルは極めて高いのが実情です。また、退職日までの有給休暇の取得申請を会社が拒否することは原則として困難です。重要なのは、トラブルが発生してから対処するのではなく、日頃から就業規則等で退職時のルールを明確に定め、退職者との間で円満な合意形成を図るプロセスを確立しておくことです。
ポイント
- ・退職時の引継ぎ義務の法的根拠と限界を理解し、実務的な対応策を立てる。
- ・有給休暇の時季変更権の制約を認識し、計画的な引継ぎを促す仕組みを整える。
- ・貸与品の返却ルールを就業規則と誓約書で明確化し、未返却リスクを未然に防ぐ。
- ・退職時のトラブルは、就業規則の整備と円満なコミュニケーションで予防する。
目次
1. 退職する社員に「引継ぎ義務」はどこまであるのか?
退職時における業務の引継ぎについて、労働基準法などの法律に「退職時の引継ぎ義務」を直接定めた条文は存在しません。しかし、労働者は労働契約上の誠実義務(民法第1条第2項)に基づき、退職にあたって会社に過大な損害を与えないよう配慮する義務を負うと解されています。業務の引継ぎは、この信義則上の義務に含まれると考えられています。
では、この義務を根拠に、引継ぎを拒否する社員に対して出社を強制できるのでしょうか。結論から言えば、困難を極めることが多いといえます。また、引継ぎが不十分であったことを理由に損害賠償を請求することも、法的には可能ですが、会社側が「引継ぎが不十分であったこと(又は行われなかったこと)」と「それによって生じた損害」との間の具体的な因果関係を立証する必要があり、そのハードルは高いと言わざるを得ません。
したがって、あらかじめ、退職者が円滑な引継ぎに協力してくれるような仕組みと関係性を築くことが最も重要になります。具体的には、就業規則に「退職する者は、会社の指示に従い、業務の引継ぎを誠実に行わなければならない」といった趣旨の規定を設けることが第一歩です。その上で、退職願が提出された際には、後任者、引継ぎ期間、引継ぎ項目を具体的に定めた「引継ぎ計画書」を作成し、双方合意の上で進めることをお勧めします。
2. 「有給休暇の消化」と引継ぎ義務が衝突した場合の実務対応
退職時のトラブルとして存在するのが、最終出社日までの期間をすべて年次有給休暇(以下「有給休暇」といいます。)の消化に充てたいという申出です。労働者が自らの有給休暇をいつ取得するかは、原則として労働者の自由であり、会社はこれを拒否できません(労働基準法第39条)。
会社には「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、取得時季を変更させる「時季変更権」が認められています(労働基準法第39条5項)。しかし、退職予定の社員の場合、退職日を超えて時季をずらすことはできないため、時季変更権の行使は事実上困難を極めます。
このような事態を避けるためには、やはり事前の備えが不可欠です。まず、就業規則において、退職の申出は「退職希望日の1か月前までに行う」ことなどを規定し、引継ぎのための期間を十分に確保できるよう努めるべきです。もちろん、この規定を設けたからといって、退職希望日が1か月を切ってから行われた退職の申出が無効になり、退職申出日から1か月後に退職の効果が生じることにはなるわけではありませんが、社内ルールとして周知することで、従業員の予測可能性を高める効果が期待できます。
また、実務的な対応としては、退職の申出があった時点で、本人と速やかに面談の機会を設けることが有効です。面談では、残りの有給休暇日数を確認した上で、会社が希望する引継ぎスケジュールを提示し、最終出社日について交渉・調整を行います。一方的に会社の都合を押し付けるのではなく、「後任者や残る同僚のために、この部分だけは責任をもって引き継いでほしい」と協力をお願いする姿勢で臨むことが、円満な解決への鍵となります。
3. トラブルを未然に防ぐ「貸与品返却ルール」の重要性
業務のために従業員へ貸与したノートパソコン、スマートフォン、社員証、制服などの返却トラブルも後を絶ちません。特に、個人情報や企業秘密が含まれる機器が返却されない場合、情報漏洩という重大な経営リスクに直結します。
まず大原則として、貸与品が返却されないことを理由に、その損害額を一方的に賃金や退職金から天引き(相殺)することは、賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)に違反するため、原則として許されません。従業員の自由な意思に基づく明確な同意があれば相殺も可能と解されていますが、賃金等との相殺について従業員が応じる可能性は低く、紛争に発展するリスクが高いため、避けるべきです。
考えられる予防策としては、入社時にあります。従業員の入社時に、「貸与物品一覧」を兼ねた誓約書を取り交わし、「退職時には会社の指示に従い、貸与品を速やかに返却すること」を約束させ、本人の署名捺印を得ておくのです。そして、退職手続きの一環として、人事担当者がその誓約書に基づき、返却物のチェックリストを作成し、最終出社日に現物を確認しながら一つずつチェックを入れていくフローを確立します。
万が一、退職後に返却がなされない場合は、まず電話やメールで督促し、それでも応じない場合は内容証明郵便で返却を請求します。それでも返却されない場合は、最終手段として、所有権に基づく返還請求や、不当利得返還請求、損害賠償請求といった法的手続きを検討することになります。このような事態を避けるためにも、入社時と退職時の手続きを制度として確立しておくことが極めて重要です。