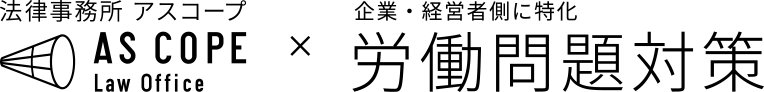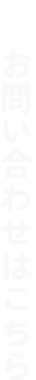退職時の引継ぎ義務とは?企業が直面するトラブルと予防策

Q
社員が退職を申し出た際、「有給休暇をすべて消化したい」「貸与品は後日返す」と主張し、十分な引継ぎをせずに退職してしまうケースがあります。結果として、取引先対応の滞りや社内業務の停滞が生じ、経営側が大きな損害を被ることも少なくありません。経営者や人事担当者としては、退職時にどの程度の引継ぎを義務づけられるのか、またトラブルを予防するためにどのような実務対応が可能かが大きな悩みとなります。
社員が退職を申し出た際、「有給休暇をすべて消化したい」「貸与品は後日返す」と主張し、十分な引継ぎをせずに退職してしまうケースがあります。結果として、取引先対応の滞りや社内業務の停滞が生じ、経営側が大きな損害を被ることも少なくありません。経営者や人事担当者としては、退職時にどの程度の引継ぎを義務づけられるのか、またトラブルを予防するためにどのような実務対応が可能かが大きな悩みとなります。
退職時の引継ぎ義務は、労働契約を根拠として認められますが、法律上明文の規定はありません。そのため、企業としては就業規則や誓約書で引継ぎルールを明確化することが重要です。裁判例や厚生労働省の指針を踏まえたうえで、トラブル防止策を事前に講じておくことで、紛争化を避け、円滑な労務管理につなげることが可能です。
ポイント
- ・退職時の引継ぎ義務を就業規則で明文化し、紛争リスクを抑制する
- ・有給休暇消化との調整を計画的に行い、労使双方の利益を守る
- ・貸与品返却ルールを徹底し、未返却による損害を予防する
- ・実務上の予防策を徹底し、労働紛争を未然に防止する
目次
1. 退職時の引継ぎ義務の法的根拠
退職時に従業員が業務を引き継ぐ義務は、労働基準法等に直接規定されているわけではありません。しかし、労働契約に基づく業務命令として引継ぎを命じることが認められています。
もっとも、就業規則や退職時の誓約書等において、業務の引継ぎを退職手続の一部として定めておくことが、紛争予防の観点からは有効です。
2. 有給休暇消化と引継ぎの調整
年次有給休暇は労働基準法第39条により労働者の権利として保障されています。したがって、原則として退職前に残日数の全てを消化することが認められます。
時季変更権の行使(労基法39条5項)も考えられないではありませんが、認められる範囲は限定的です。そのため、早期に退職の意思表示を受け、計画的に有給休暇の消化と引継ぎを組み合わせることが、現実的な対応となります。
3. 貸与品返却を巡るトラブルと対応策
退職時には、パソコンやスマートフォン、セキュリティカードといった会社貸与品の返却が不可欠です。これらの未返却は、情報漏洩や設備利用のリスクに直結します。
実務上は、就業規則や雇用契約書に「貸与品は退職日までに返却する」と明示し、返却リストを作成して管理することが推奨されます。加えて、返却方法(郵送とするのか、費用はどちらの負担とするのか等)についても定めておくと良いでしょう。
また、会社に放置された私物の処分を会社に一任する旨の規定も盛り込んでおくことで、逆に私物を会社に放置された場合への手当も可能です。
4. 企業が取るべき予防策と実務対応
以上を踏まえ、企業としては以下のような予防策を講じることが有効です。
第一に、就業規則に「退職時の業務引継ぎ・貸与品返却」を明記すること。第二に、退職意思表示を受けた段階で、有給休暇消化との調整計画を提示すること。第三に、誓約書やチェックリストを活用し、引継ぎと返却を確実に履行させることです。
これらを事前に制度化しておくことで、従業員の権利を尊重しつつ、企業経営への悪影響を最小化できます。