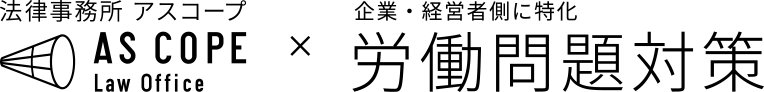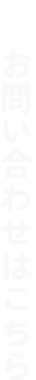企業を守る!弁護士が説く懲戒処分の適正な運用ルール

Q
従業員の規律違反や問題行動に対し、企業として厳正な態度で臨みたいと考えています。しかし、懲戒処分を行うにあたり、どのような種類があり、どのような基準で処分を決定すればよいのか、法的に問題のない進め方がわからず不安です。特に、処分対象者への「弁明の機会の付与」が重要と聞きますが、具体的にどう対応すれば良いのでしょうか。また、万が一、懲戒処分が「懲戒権の濫用」と判断された場合のリスクも懸念しており、企業としてどのような点に注意すれば、紛争を未然に防ぎ、適正な処分と言えるのか、専門家の具体的なアドバイスが欲しいです。
従業員の規律違反や問題行動に対し、企業として厳正な態度で臨みたいと考えています。しかし、懲戒処分を行うにあたり、どのような種類があり、どのような基準で処分を決定すればよいのか、法的に問題のない進め方がわからず不安です。特に、処分対象者への「弁明の機会の付与」が重要と聞きますが、具体的にどう対応すれば良いのでしょうか。また、万が一、懲戒処分が「懲戒権の濫用」と判断された場合のリスクも懸念しており、企業としてどのような点に注意すれば、紛争を未然に防ぎ、適正な処分と言えるのか、専門家の具体的なアドバイスが欲しいです。
懲戒処分は企業秩序を維持するために不可欠な措置ですが、その運用を誤ると「懲戒権の濫用」として無効となるリスクを孕んでいます。重要なのは、就業規則に懲戒の種類と事由を明確に定め、事実に即した客観的な証拠に基づき、適正な手続を踏むことです。特に、処分対象者に十分な「弁明の機会の付与」を行うことは、手続の公正性を担保する上で極めて重要です。本記事では、懲戒処分の具体的な種類と基準、弁明の機会の適切な付与方法、そして懲戒権の濫用と判断されないための実務上の注意点について、企業側の視点から弁護士が分かりやすく解説します。
ポイント
- ・懲戒処分の種類と基準を就業規則へ明確に定め、公正な処分判断の基盤を整備する。
- ・処分対象者へ「弁明の機会」を付与し、手続の適法性を確保する。
- ・客観的証拠に基づき慎重に事実認定を行い、懲戒権濫用リスクを徹底的に回避する。
- ・懲戒処分の有効性を高めるため、日頃から専門家(弁護士)へ相談できる体制を構築する。
目次
1. 懲戒処分とは?~企業秩序維持の根幹~
懲戒処分とは、企業が従業員の企業秩序違反行為に対して科す処分です。企業が健全な事業活動を継続し、良好な職場環境を維持するためには、従業員が遵守すべき服務規律や業務命令が存在し、これらに違反した場合には、一定の措置をとることで企業秩序を回復・維持する必要があります。
この懲戒権の根拠は、一般的には労働契約に内包される使用者の包括的な人事権や企業秩序維持権に由来すると解されています。そして、労働契約法第15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めており、懲戒権の行使には一定の法的制約があることを明確にしています。
実務上、企業が懲戒処分を有効に行うためには、あらかじめ就業規則に懲戒の種類及び事由を定めておくことが不可欠です。労働基準法第89条第9号は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成・届出義務を課しており、その中で「制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を記載しなければならないと定めています。就業規則に具体的な懲戒事由とそれに対応する懲戒処分の種類が明記されていなければ、原則として懲戒処分を行うことはできません。したがって、企業としては、自社の実態に即した具体的かつ明確な懲戒規定を整備することが、適正な労務管理の第一歩となります。
2. 懲戒処分の種類と基準~事案に応じた処分の選択と就業規則の重要性~
懲戒処分には、その重さに応じていくつかの種類があります。軽いものから順に、戒告・譴責(将来を戒める)、減給(給与から一定額を差し引く)、出勤停止(一定期間の就労を禁止し、その間の賃金は支払わない)、降格(役職や職位を引き下げる)、諭旨解雇(解雇に相当するが、まずは退職を勧告し、応じない場合に懲戒解雇とする)、そして最も重い懲戒解雇(予告なしに即時解雇、退職金不支給または減額となることが多い)などが一般的です。
| 懲戒処分の種類 | 処分の重さ(一般的な目安) |
|---|---|
| 戒告・譴責 | 軽 |
| 減給 | ↓ |
| 出勤停止 | 中 |
| 降格 | ↓ |
| 諭旨解雇 | 重 |
| 懲戒解雇 | 最重 |
後記4.のとおり、いずれの懲戒処分を選択するかは、問題となった従業員の行為の態様、頻度、結果の重大性、企業への影響度、本人の反省の度合い、過去の処分歴などを総合的に考慮して決定する必要があります。この「処分の相当性」が、後に懲戒権の濫用か否かを判断する上で重要な要素となります。
就業規則には、これらの懲戒処分の種類とともに、それぞれどのような場合に科されるのか(懲戒事由)を具体的に定める必要があります。例えば、「正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及んだとき」「許可なく会社の物品を持ち出したとき」「業務に関連し、重大なハラスメント行為を行ったとき」など、できる限り具体的に記載することが望ましいです。懲戒事由に定められていない事由による懲戒処分は無効となるため、厚生労働省が公表している「モデル就業規則」等を丸写しするのではなく、自社の業種、規模、企業文化などを踏まえてカスタマイズすることが肝要です。
3. 適正な懲戒処分の進め方~「弁明の機会の付与」を確実に実施する~
懲戒処分を有効に行うためには、後記4.の実体的な理由(懲戒事由の存在と処分の相当性)だけでなく、手続の適正も極めて重要です。不適切な手続は、懲戒処分が無効と判断される大きな要因となります。
まず、懲戒処分の対象となる事実について、客観的な証拠に基づき、徹底した調査を行う必要があります。関係者からのヒアリング、メールや業務日報の確認、防犯カメラ映像の解析など、先入観を排して慎重に事実を認定します。憶測や伝聞だけで処分を決定することは厳に慎まなければなりません。
そして、最も重要な手続の一つが「弁明の機会の付与」です。これは、懲戒処分を検討している対象従業員に対し、企業側が把握している問題行動や懲戒事由の具体的な内容を告げ、それに対して反論や釈明、有利な証拠を提出する機会を与えることを意味します。弁明の機会は、書面で通知し、指定した日時・場所で口頭にて聴取する方法(記録のため複数名で対応し、議事録を作成する)や、期限を定めて弁明書を提出させる方法などがあります。いずれの方法を採るにしても、従業員が十分に準備して反論できるよう、相当な期間を与える配慮が必要です。この弁明の機会を適切に付与しなかった場合、他の要件を満たしていても懲戒処分が無効とされるリスクが高まります。
その他、企業によっては、懲戒委員会を設置し、そこで処分の妥当性を審議するケースもあります。これは法律上の義務ではありませんが、処分の公正性・客観性を高める上で有効な手段となり得ます。最終的に懲戒処分を決定した場合には、処分対象者に対し、懲戒処分の種類、処分理由(根拠となる就業規則の条項を含む)、処分日などを記載した「懲戒処分通知書」を交付します。
4. 懲戒権の濫用と判断されないための具体的防止策
労働契約法第15条に定められる「懲戒権の濫用」と判断されることを避けるためには、以下の重要な原則を遵守する必要があります。
第一に、「客観的に合理的な理由」の存在です。これは、懲戒処分の対象となる従業員の行為が、就業規則上の懲戒事由に該当し、かつ、その行為が懲戒処分を科すに値する程度の規律違反であることを意味します。単なる些細なミスや、就業規則に明記されていない事由に基づく処分は、合理的な理由を欠くと判断される可能性が高いです。
第二に、「社会通念上の相当性」です。これは、問題となった行為の性質・ 態様、結果の重大性、従業員の勤務態度や過去の非違行為の有無、反省の度合い、他の従業員との均衡などを総合的に考慮して、科される懲戒処分が相当であるかという観点を意味します。中でも、懲戒解雇という最も重い処分を選択する際には、極めて慎重な判断が求められます。問題行為・非違行為がよほど重大なものでない限りは、他の懲戒処分を複数回科す、従業員の問題行為の原因を取り除く等、解雇回避措置を講じたものの、当該処分事由に関して改善の余地がなく、企業にとっても他に尽くす手段がないといった状態になって初めて、懲戒解雇を検討するべきであるといえます。
第三に、「平等取扱いの原則」です。同様の規律違反行為に対しては、原則として同様の懲戒処分を科すべきであり、特定の従業員に対してのみ不当に重い処分を科したり、逆に不当に軽い処分で済ませたりすることは、公平性を欠き、懲戒権の濫用と評価されるリスクがあります。
これらの原則を踏まえ、企業が懲戒権の濫用と判断されないためには、以下の防止策を講じることが重要です。
- ・就業規則の整備と周知徹底:懲戒事由と懲戒の種類を明確かつ具体的に定め、従業員に周知すること。
- ・客観的証拠に基づく事実認定:思い込みや伝聞ではなく、客観的な証拠等の信用性が高い証拠に基づいて事実を認定すること。
- ・適正手続の遵守:特に弁明の機会の付与を確実に行うこと。
- ・処分の相当性の吟味:問題行動と処分の重さのバランスを慎重に検討すること。
- ・記録の作成と保管:調査記録、弁明の機会の聴取記録、懲戒委員会の議事録、懲戒処分通知書などを適切に作成・保管すること(これらの記録は、万が一紛争になった場合に企業側の正当性を主張する上で不可欠な証拠となります。)。
- ・専門家への相談:懲戒処分の実施を検討する際には、事前に労働問題に詳しい弁護士に相談し、法的な妥当性やリスクについて助言を受けることが、紛争予防の観点から極めて有効です。
懲戒処分は、企業秩序を守るための最後の手段とも言えます。その行使にあたっては、常に慎重かつ公正な対応を心がけ、従業員との信頼関係を損なうことのないよう努めることが、企業の持続的な発展に繋がります。