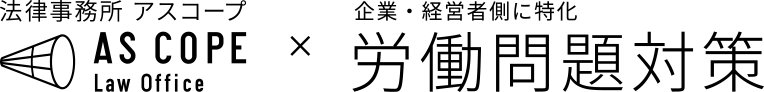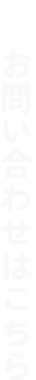企業が注意すべき労働者派遣の活用ポイント

Q
当社では、業務の繁閑に合わせて労働者派遣を柔軟に活用したいと考えています。しかし、過去に派遣社員との間でトラブルがあったという話も聞き、知らないうちに法律に違反していないか、あるいは「偽装請負」を疑われないかと不安です。派遣社員を受け入れる際に、企業として具体的にどのような点に注意し、どのような法的義務を遵守すれば、リスクを抑えつつ適切に活用できるのでしょうか。派遣社員の能力を最大限に引き出し、円滑な事業運営につなげるための実践的なアドバイスが欲しいです。
当社では、業務の繁閑に合わせて労働者派遣を柔軟に活用したいと考えています。しかし、過去に派遣社員との間でトラブルがあったという話も聞き、知らないうちに法律に違反していないか、あるいは「偽装請負」を疑われないかと不安です。派遣社員を受け入れる際に、企業として具体的にどのような点に注意し、どのような法的義務を遵守すれば、リスクを抑えつつ適切に活用できるのでしょうか。派遣社員の能力を最大限に引き出し、円滑な事業運営につなげるための実践的なアドバイスが欲しいです。
労働者派遣の活用は、企業にとって有用な人材確保の手段ですが、労働者派遣法に基づく厳格なルールを遵守する必要があります。派遣先企業は、派遣契約の適切な締結、派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成・通知、苦情処理体制の整備などが求められます。特に、派遣労働者への指揮命令関係を明確にし、「偽装請負」と疑われるような状況を避けることが極めて重要です。本記事では、企業が労働者派遣を適法かつ効果的に活用するために押さえておくべき法的義務と実務上のポイントを、企業側の視点から具体的に解説します。
ポイント
- ・労働者派遣法を遵守し、派遣先企業の法的責任を理解する。
- ・「偽装請負」を回避し、適正な指揮命令関係を維持する。
- ・派遣契約の内容を精査し、派遣社員との良好な協働関係を構築する。
- ・紛争リスクを低減するため、苦情処理体制を整備・運用する。
目次
1. 労働者派遣の基礎知識と企業側の留意点
労働者派遣とは、派遣元事業主(派遣会社)が自己の雇用する労働者(派遣労働者)を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることをいい、派遣先に対して派遣労働者を派遣先に雇用させることを約してするものを含まないものをいいます(労働者派遣法第2条第1号)。企業が労働者派遣を活用する主なメリットとしては、必要な時に必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できる点、採用や労務管理にかかるコスト・手間を軽減できる点などが挙げられます。特に、専門性の高い業務や一時的な業務量の増加に対応する際に有効です。
しかし、企業側(派遣先)は、これらのメリットを享受する一方で、労働者派遣法に基づく様々な義務を負うことを理解しておく必要があります。派遣労働者は派遣元と雇用契約を締結していますが、実際の就業場所は派遣先であり、業務に関する指揮命令も派遣先から受けます。このため、派遣労働者の保護と適正な就業環境の確保は、派遣元だけでなく派遣先にも求められる重要な責務です。
具体的には、労働時間管理、安全衛生の確保、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止措置など、自社の従業員と同様に配慮すべき事項が多数存在します。これらの法的義務を怠った場合、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、派遣労働者との間で紛争が生じるリスクも高まります。したがって、労働者派遣を単なる「便利な外部リソース」と捉えるのではなく、法制度を正しく理解し、適切な受け入れ体制を整備することが不可欠です。
2. 派遣先企業に課される法的義務と遵守事項
労働者派遣法では、派遣先企業に対して多岐にわたる措置を講じることを義務付けています。これらは派遣労働者の保護と、労働者派遣の適正な運用を確保するために不可欠なものです。企業の人事労務担当者や経営者は、これらの義務を正確に把握し、遵守体制を構築しなければなりません。
まず基本となるのが、労働者派遣契約の適切な締結です。契約には、業務内容、就業場所、指揮命令者、派遣期間、就業日・時間、安全衛生に関する事項などを明確に定める必要があります(労働者派遣法第26条)。契約内容が曖昧であると、後のトラブルの原因となり得ます。
次に、派遣先責任者の選任も義務付けられています(労働者派遣法第41条)。派遣先責任者は、派遣労働者からの苦情処理、派遣元との連絡調整などを行う役割を担います。適切な人物を選任し、その職務を周知することが求められます。
また、派遣先管理台帳の作成・保管・通知義務も重要です(労働者派遣法第42条)。派遣先管理台帳には、派遣労働者の氏名、派遣就業をした日、始業・終業時刻、従事した業務の種類などを日々記録し、一定期間保管するとともに、その内容を派遣元に通知しなければなりません。これは、派遣労働者の就業実態を正確に把握し、適正な労務管理を行うための基礎資料となります。
さらに、派遣労働者からの苦情の申出を受ける者、苦情処理方法、派遣元との連携体制の確立も派遣先の責務です(労働者派遣法第40条第1項)。苦情に対しては、誠実かつ遅滞なく対応し、派遣元とも連携してその処理にあたる必要があります。
これらの義務を遵守することは、法令違反によるリスクを回避するだけでなく、派遣労働者が安心して能力を発揮できる環境を整備し、結果として企業の生産性向上にも繋がるという認識を持つことが肝要です。
3. 「偽装請負」のリスクと判断基準
労働者派遣と混同されやすく、企業が特に注意すべき法的問題の一つに「偽装請負」があります。偽装請負とは、契約形式上は請負契約でありながら、実態としては労働者派遣に該当する状態を指します。これは労働者派遣法や職業安定法に違反する行為であり、発覚した場合には罰則が科されるほか、企業の社会的信用を大きく損なうリスクがあります。
請負契約においては、注文主(委託者)は受託者に対し、仕事の完成を目的として業務を委託し、受託者は自己の裁量と責任において業務を遂行します。注文主が受託者の労働者に対して直接指揮命令を行うことは原則としてありません。これに対し、労働者派遣では、派遣先が派遣労働者に対して直接指揮命令を行います。この指揮命令関係の有無が、請負と労働者派遣を区別する最も重要な判断基準の一つです。
厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)では、以下の2つの要件をいずれも満たす場合に「請負」と判断されるとしています。
- 自己の雇用する労働者の労働力を他人(注文主)の指揮命令の下に労働させるものでないこと。
- 請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方(注文主)から独立して処理するものであること。
具体的には、注文主が業務の遂行方法や労働時間、服務規律などについて、受託者の労働者に対して指示を出していないか、勤怠管理を直接行っていないか、などがチェックポイントとなります。
偽装請負と判断された場合、派遣先(実質的な使用者)には、労働者派遣法に基づく派遣先の義務違反が問われるだけでなく、職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)に該当する可能性もあります。また、その労働者との間で黙示の雇用契約が成立していると判断され、直接雇用の責任が生じるケースも考えられます。企業としては、契約の名称だけでなく、業務の実態を常に精査し、偽装請負に該当しないよう細心の注意を払う必要があります。
4. 適法かつ効果的な労働者派遣活用のための実務対応
労働者派遣を適法かつ効果的に活用するためには、法遵守はもちろんのこと、派遣労働者がその能力を十分に発揮できるような実務上の配慮が不可欠です。以下に、企業が取り組むべき具体的な実務対応のポイントを挙げます。
まず、派遣契約締結時の内容確認の徹底です。派遣元から提示される契約書案を鵜呑みにせず、自社の業務実態に即しているか、法令に適合しているかを法務担当者や弁護士も交えて確認することが望ましいでしょう。特に、業務内容、指揮命令系統、責任範囲、派遣期間制限(いわゆる「事業所単位の期間制限」や「個人単位の期間制限」)については、誤解や認識の齟齬がないよう慎重にすり合わせる必要があります。
さらに、事前の面接・選考行為が禁止である点も重要です。派遣先は、派遣される労働者を事前に面接することや、履歴書・職務経歴書を提出させて、候補者の中から特定の人選を行うことは原則として禁止されています(労働者派遣法第26条第6項の趣旨)。誰を派遣するかを決定するのは、雇用主である派遣元の責任です。派遣先が行うと、職業安定法が禁じる「労働者供給事業」に抵触する「偽装請負」の一形態と見なされるリスクがあります。業務に必要なスキルや経験については、派遣契約の段階で派遣元に明確に伝えるようにしてください。
次に、指揮命令関係の明確化と適切な運用です。派遣労働者に対して業務指示を行うのは、あらかじめ定められた派遣先の指揮命令者に限定すべきです。指揮命令者以外の者が指示を出したり、契約外の業務を依頼したりすることは、トラブルの原因となるだけでなく、偽装請負を疑われる要因にもなりかねません。指揮命令者には、労働者派遣法の基本知識や、派遣労働者への適切な接し方について教育を行うことも有効です。
加えて、派遣労働者の待遇確保(同一労働同一賃金)への協力も重要です。2020年の法改正により、派遣労働者の不合理な待遇差を解消する「同一労働同一賃金」が厳格化されました。これに伴い、派遣先は派遣元に対し、比較対象となる自社の労働者(通常の労働者)の賃金や福利厚生に関する情報を提供する法的義務(労働者派遣法第31条の2第2項)を負います。
また、自社の従業員に利用を認めている福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)については、派遣労働者にも利用の機会を与えなければなりません(同法第40条第3項)。これらの協力義務を怠ることは、法令違反となるだけでなく、派遣労働者のモチベーション低下や紛争の原因となります。
また、派遣労働者に対しても、教育訓練機会の提供への配慮が求められる場合があります(労働者派遣法第40条第2項努力義務)。業務に必要な知識やスキルを習得するためのOJTや研修機会について、派遣元と協議し、可能な範囲で協力することが、派遣労働者のモチベーション向上と戦力化に繋がります。
最後に、派遣社員との日頃のコミュニケーションも重要です。業務上の指示だけでなく、職場環境に関する意見を聞く機会を設けるなど、良好な関係構築に努めることで、潜在的な不満や問題を早期に把握し、紛争を未然に防ぐことができます。ただし、過度な一体化は、直接雇用と誤認されるリスクもはらむため、節度ある対応が求められます。あくまでも派遣契約に基づいた関係であることを念頭に置く必要があります。
5. 派遣労働者を巡る紛争予防と対応策
どれほど注意を払っていても、派遣労働者を巡る紛争のリスクを完全にゼロにすることは困難です。そのため、紛争を未然に防ぐための体制整備と、万が一紛争が発生した場合の適切な対応策を準備しておくことが企業防衛の観点から重要となります。
紛争予防の第一歩は、前述の通り、労働者派遣法及び関連法令の遵守徹底です。特に、派遣先管理台帳の正確な記録、苦情処理体制の整備と実効性のある運用は、紛争の芽を早期に摘み取る上で不可欠です。派遣労働者が気軽に相談できる窓口を設け、寄せられた苦情や相談には迅速かつ誠実に対応する姿勢を示すことが、信頼関係の構築に繋がります。
また、派遣契約期間中のハラスメント防止措置の徹底も極めて重要です。派遣労働者も、派遣先の従業員と同様に、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントから保護される権利があります。派遣先は、自社の従業員に対するのと同様の防止措置を講じる義務があります(男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法)。相談窓口の設置、研修の実施、ハラスメント発生時の厳正な対処などを通じて、ハラスメントの起きない職場環境づくりに努めるべきです。
万が一、派遣労働者との間で紛争が発生し、当事者間での解決が困難な場合には、早期に弁護士などの専門家に相談することを強く推奨します。労働紛争は、初期対応の誤りが事態を悪化させることが少なくありません。企業側の代理人として、法的リスクを正確に評価し、企業にとって最善の解決策を助言できる専門家のサポートを得ることは、紛争の拡大を防ぎ、迅速かつ適切な解決を図る上で非常に有効です。特に、労働審判や訴訟に発展する可能性がある場合には、法的な専門知識と交渉力が不可欠となります。