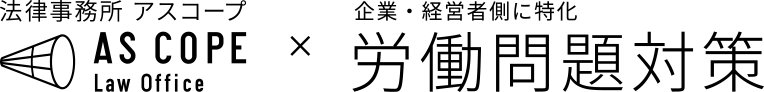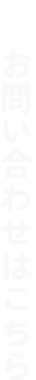テレワークガイドライン改定で何が変わる?押さえておきたい労務管理のポイント

Q
コロナ禍で急速に普及したテレワーク(リモートワーク)ですが、コロナ収束が見え始めた後も、働き方改革の一環として継続・拡大する企業が増えています。同時に、厚生労働省などの行政機関はテレワークに関するガイドラインを随時改定し、企業として押さえるべき法的ポイントや労務管理方法を更新し続けています。
在宅勤務時の労働時間管理や通信費・光熱費の負担、情報セキュリティ対策など課題は山積みですが、今回のガイドライン改定で具体的に何が変わり、企業はどんな視点で対応を検討すればよいのでしょうか。
コロナ禍で急速に普及したテレワーク(リモートワーク)ですが、コロナ収束が見え始めた後も、働き方改革の一環として継続・拡大する企業が増えています。同時に、厚生労働省などの行政機関はテレワークに関するガイドラインを随時改定し、企業として押さえるべき法的ポイントや労務管理方法を更新し続けています。
在宅勤務時の労働時間管理や通信費・光熱費の負担、情報セキュリティ対策など課題は山積みですが、今回のガイドライン改定で具体的に何が変わり、企業はどんな視点で対応を検討すればよいのでしょうか。
テレワークガイドラインの改定は、従業員保護と企業の安全配慮義務を両立させるために必要な指針をアップデートし続けています。改定の度に、労働時間の正確な把握方法や在宅勤務における費用負担の原則、情報漏えいリスクへの対策などの項目に追加・変更が生じるため、企業は就業規則や勤怠管理システムを随時見直す必要があります。
ただし、改定内容を漫然と取り入れるだけでは、コスト負担とのバランスを取れないなど現実の経営判断では難しいかもしれません。経営者目線からは、無制限の費用負担や過度なセキュリティ要求は企業体力を圧迫する恐れがあるため、自社の規模・業種・社員構成に合った形で、法令を守りながらトラブルを避ける運用設計が重要です。万が一、長時間労働が放置されていたり、費用負担やセキュリティの曖昧さが原因でトラブルが生じると、労基法違反の問題や情報漏えいによる信用低下といったリスクにさらされる可能性もあるので注意が必要です。
ポイント
- ・在宅勤務の労働時間を正しく把握する仕組み:未払残業代や健康障害のリスクを防ぐため、打刻やログの活用を慎重に設計。
- ・費用負担の区分を明確化し、就業規則で定義:通信費や光熱費、備品購入費などの範囲を事前に設定して、後から「想定外の負担」をしなくて済むようにする。
- ・情報セキュリティ対策の再点検:VPNや暗号化通信など技術面だけでなく、社内データのアクセス範囲や違反時の懲戒規程を明文化しておく。
目次
1.テレワークガイドラインの改定背景と意図
新型コロナウイルス流行時に急増した在宅勤務ですが、アフターコロナでも「働き方の多様化」を推進する目的から、テレワークを継続する企業は少なくありません。ガイドラインは、こうした流れに対応するために、労使双方のトラブルを避けるための指針を随時更新しています。具体的には、労働時間の把握方法や健康管理義務、費用負担の原則などに言及し、企業が実務上どこまで責任を負うべきかを一定の方向性として示しているのです。 ただし、ガイドラインはあくまでも行政が示す「望ましい実務」のモデルであり、実際の職場での運用は企業ごとの実情やコスト面の許容度、さらには従業員構成に合わせてカスタマイズすることが必要でしょう。
2.労働時間管理の実務ポイント
テレワークで最も懸念されるのが、従業員が実際に「何時間働いているか」を正確に把握しにくい点です。ここを曖昧にしてしまうと、未払残業代を請求されるリスクや、長時間労働による健康障害が起きた際に企業の安全配慮義務違反を問われる恐れがあります。 そのため、従業員が在宅勤務時でもログイン・ログアウトの打刻やアプリを活用した勤怠システムを用い、労働時間を客観的に管理する仕組みを整えることが望ましいです。もっとも、企業規模によっては高額なシステム導入が難しい場合もあり、その場合にはExcelや簡易的なクラウドツールを活用したり、フレックスタイム制などを使って柔軟な運用を検討するなど、経営判断とコストバランスを考慮した選択が大切です。
3.費用負担と情報セキュリティへの対応
在宅勤務では、通信費や光熱費など、どこまで企業が負担するかがよく問題になります。ガイドライン上は「費用負担を明確にし、できるだけ従業員に不利益がないように努めること」が望ましいとされていますが、無制限に企業が負担すれば経営的に重荷になりかねません。 そこで、就業規則や雇用契約書に「費用負担の考え方」を明示することが基本的なアプローチとなります。たとえば、通信費は一定額まで企業が支給し、それを超える分は自己負担とする方法や、日額または月額の在宅勤務手当を定めるケースなど、運用ルールは各社の状況次第です。また、情報漏えいのリスクに備えて、VPNや端末のセキュリティ設定を義務づけ、違反時のペナルティを就業規則に盛り込むなど、明確化することも必須となります。
4.まとめ
テレワークガイドラインの改定は、単なる形式的なルール追加ではなく、企業が法令順守と柔軟な働き方を両立させるための重要な指針を提供しています。しかし、実務的には「コストと効果のバランス」「システム導入や従業員教育にかかる負担」が避けられず、経営判断が伴う分野です。特に中小企業では、費用負担をどこまで許容できるか、どのくらいシステムを活用できるかを慎重に検討する必要があります。 当事務所では、弁護士がテレワークにおける労働時間管理や費用負担ルールの法的リスクを評価し、税理士・社労士との連携で補助金活用や勤怠システム導入に関するアドバイスも一括して行えます。改定されたガイドラインに対応しながら、トラブルなくテレワークを継続・定着させたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。