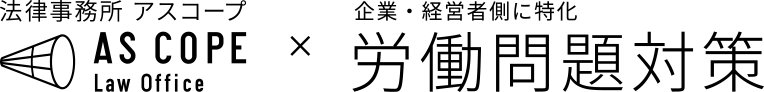フレックスタイム制導入の鍵「労使協定」の定め方と残業管理の注意点

Q
優秀な人材の確保と定着のため、柔軟な働き方を可能にするフレックスタイム制の導入を検討しています。しかし、何から手をつければ良いのか、法的にどのような手続きが必要なのか分かりません。特に「労使協定」が重要だと聞きますが、具体的に何を定めれば良いのでしょうか。また、労働時間が従業員任せになることで、残業代の計算が複雑になり、未払い残業代のリスクが高まるのではないかと懸念しています。
優秀な人材の確保と定着のため、柔軟な働き方を可能にするフレックスタイム制の導入を検討しています。しかし、何から手をつければ良いのか、法的にどのような手続きが必要なのか分かりません。特に「労使協定」が重要だと聞きますが、具体的に何を定めれば良いのでしょうか。また、労働時間が従業員任せになることで、残業代の計算が複雑になり、未払い残業代のリスクが高まるのではないかと懸念しています。
フレックスタイム制を適法に導入するには、就業規則にフレックスタイム制について規定した上で、労働者の過半数代表者との間で「労使協定」を締結することが不可欠です。労使協定では、対象労働者の範囲、清算期間、精算期間における総労働時間、コアタイム等を具体的に定める必要があります。フレックスタイム制における残業は、「清算期間における法定労働時間の総枠」を超えた時間で計算するため、その残業管理方法を正確に理解することが極めて重要です。協定の不備や運用を誤ると制度自体が無効と判断されるリスクがあるため、専門家による法的な確認が欠かせません。
ポイント
- ・労使協定の必須事項を網羅し、制度が無効と判断される法的リスクを回避する。
- ・自社の繁閑に合わせた「清算期間の設定」を行い、柔軟な労働時間管理を実現する。
- ・フレックスタイム制特有の残業計算を正確に理解し、未払い賃金請求を未然に防ぐ。
- ・就業規則と労使協定の両方を整備し、制度導入の法的根拠を盤石にする。
目次
1. フレックスタイム制導入の前提となる就業規則と労使協定の法的役割
フレックスタイム制は、従業員が日々の始業・終業時刻を自主的に決定できる、柔軟性の高い労働時間制度です。しかし、この制度を企業が有効に導入するためには、労働基準法に則り厳格な手続きを踏む必要があります。その手続きの根幹をなすのが、就業規則への規定と労使協定の締結です。
まず、就業規則において「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる」旨を定めなければ、制度の根拠規定が欠けることになります。これは、従業員に対してフレックスタイム制が適用されることを包括的に明示するために不可欠です。
その上で、制度の具体的な内容を定めるのが労使協定の役割です。労働基準法第32条の3は、労使協定によって対象労働者の範囲や清算期間などを定めることを要求しています。つまり、就業規則が「フレックスタイム制を導入します」という宣言し、労働者の労働条件とするための手続きであるとすれば、労使協定は「その制度は、いつからいつまで、誰を対象に、どのようなルールで運用します」という詳細な設計図にあたります。この両方が揃って初めて、企業は労働者に法定労働時間を超えて労働させても、直ちに残業代の支払い義務が生じるわけではないという、フレックスタイム制の法的効果を享受できるのです。どちらか一方でも欠けていれば、制度は法的に無効と判断されかねないため、両輪での整備が必須となります。
2. 【法的要件】フレックスタイム制の労使協定で必ず定めるべき事項
フレックスタイム制の労使協定は、単なる努力目標を記すものではなく、法が定める必須事項を漏れなく記載しなければ効力を持ちません。具体的には、以下の項目を定める必要があります。
一つ目は「対象となる労働者の範囲」です。全従業員を対象とするのか、あるいは特定の部署や職種(例:営業部、企画開発職)に限定するのかを明確に定めます。範囲を曖昧にすると、後に対象者性を巡るトラブルに発展する可能性があります。
二つ目は「清算期間」です。これは、労働時間を精算する期間のことで、最長で3箇月以内の期間(※)で設定します。※ 2019年4月法改正
三つ目は「清算期間における総労働時間」です。これは「清算期間における所定労働時間」とも言い換えられ、この時間を超えて労働した分が残業時間の計算の基礎となります。この総労働時間は、清算期間内の法定労働時間の総枠を超えない範囲で設定しなければなりません。
四つ目は「標準となる1日の労働時間」です。これは有給休暇を取得した際に支払われる賃金の計算基礎などに用いられます。
そして、任意ではありますが、「コアタイム」(必ず勤務すべき時間帯)と「フレキシブルタイム」(その時間帯内であればいつでも出退勤できる時間帯)を設ける場合は、その具体的な時間帯を協定で定める必要があります。これらの項目に一つでも不備があれば、労働基準監督署の調査等で制度の有効性を否定されるリスクがあるため、細心の注意を払って作成しなければなりません。
3. 法改正の活用:「清算期間の設定」が柔軟な働き方を実現する
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、フレックスタイム制の清算期間の上限が従来の1箇月から3箇月に延長されました。これは、企業にとって制度活用の幅を大きく広げる重要な改正です。
例えば、清算期間を3箇月と設定した場合、月ごとの繁閑に合わせて労働時間を柔軟に調整することが可能になります。1箇月目が繁忙期で法定労働時間を超えて働いたとしても、2箇月目や3箇月目が閑散期であれば、その期間内で労働時間を短くすることで、3箇月の総労働時間を法定の枠内に収めることができます。これにより、月単位では時間外労働として割増賃金の支払いが必要だったケースでも、3箇月単位で調整することで、割増賃金の発生を抑制するよう努めることが可能です。
※精算期間が1箇月を超える制度にした場合には、一月あたりで法定労働時間を超えても残業時間とならない範囲には限界があるため注意が必要です(後記4の①、②参照)。
ただし、この柔軟性を享受するには、新たな義務も課されます。清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制を導入する場合、締結した労使協定を所轄の労働基準監督署長へ届け出る義務が生じます。1箇月以内の場合は届出不要であるため、この違いは実務上、非常に重要です。また、清算期間の途中で退職した従業員の賃金精算ルールなども、あらかじめ就業規則等で定めておくことが望ましいでしょう。清算期間の設定は、企業の業務実態に合わせて戦略的に行うことで、生産性の向上と労務コストの最適化を両立させる鍵となります。
4. 紛争の火種となる「残業管理方法」と未払い賃金リスク
フレックスタイム制で最も誤解が生じやすく、労務紛争に発展しやすいのが残業管理方法です。通常の勤務形態のように「1日8時間、週40時間」を超えたら即残業、という単純な計算にはなりません。
フレックスタイム制における時間外労働(残業)は、「清算期間における実労働時間が、法定労働時間の総枠を超えた時間」を指します。この「法定労働時間の総枠」は、以下の計算式で算出されます。
週の法定労働時間(40時間) × 清算期間の暦日数 ÷ 7日
例えば、暦日数が31日の月であれば、40時間 × 31日 ÷ 7日 = 177.1時間 が法定労働時間の総枠となります。労使協定で定めた総労働時間(所定労働時間)が160時間であった場合、実労働時間が180時間だった従業員は、177.1時間を超えた2.9時間が時間外労働として割増賃金の対象となり、160時間から177.1時間の間の17.1時間は法定内残業となります。
さらに、清算期間が1箇月を超える場合は、管理がより複雑になります。その場合、①1箇月ごとに週平均50時間を超えた労働時間、および、②清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えた労働時間(①で支払った時間を除く)について、それぞれ割増賃金の支払いが必要となります。この計算を誤ると、意図せず未払い残業代が発生し、労働基準監督署からの是正勧告や、従業員からの労働審判・訴訟といった深刻な事態を招きかねません。正確な勤怠管理システムの導入と、法に則った計算方法の徹底が不可欠です。