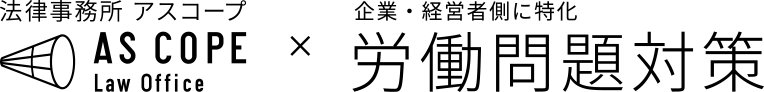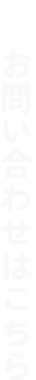使用者の配転命令権の存否と合意原則についての判例解説(最二小判令和6年4月26日)

目次
| 【本稿は2025年1月号のニュースレターにて執筆されたものです】 ASCOPEでは企業活動に関わる法改正や制度の変更等、毎月耳よりの情報をニュースレターの形で顧問先の皆様にお届けしております。 会社法務に精通した社会保険労務士、顧問弁護士をお探しの企業様は、是非ASCOPEにご依頼ください。 |
使用者には人事権行使の一環として労働者に対して配転(配置転換や転勤)を命じる権利が認められていますが、今年の4月に、「職種限定合意」が認定される場合における使用者の配転命令権の有無について判断を示した最高裁の判決がありました。そこで、本NewsLetterでは、上記の判断をした最高裁判所第二小法廷令和6年4月26日判決・労働判例1308号5頁(以下では「本判例」といいます。)についての解説をさせていただきます。
1 配転について
(1) はじめに
本判例の解説に入る前に、配転についてご説明いたします。
配転とは、従業員の配置の変更であって、同一企業内の職種・職務内容・勤務場所のいずれかを、長期間にわたって変更する企業内人事異動の1つです。同一勤務地内の所属部署の変更が「配置転換」、勤務地の変更が「転勤」といわれます。
(2) 配転命令の有効性の判断枠組み
長期的な雇用を予定した正社員については、職種・職務内容や勤務地を限定せずに採用され、企業組織内での従業員の職業能力や地位の発展や労働力の補充・調整のために系統的で広範囲な配転が実施されることが通例です。
配転命令権の有効性を判断したリーディングケースとしては、東亜ペイント事件(最高裁第二小法廷判決昭和61年7月14日労働判例477号6頁)が挙げられます。
同裁判例は、配転命令の有効性について、①配転命令権の有無(使用者が労働者に対して配転命令権を有するか)、②配転命令権の濫用の有無(使用者に労働者に対する配転命令権が認められるとして、その行使が権利濫用と評価されるかどうか)の二段階の審査基準での判断を示し、以降の配転命令権の有効性判断に大きな影響を及ぼしました。
具体的には、①配転命令権の有無は、❶就業規則等に包括的な配転命令権の規定があるか、❷配転の実施の頻度、❸職種・勤務地限定合意の有無という考慮要素を加味して判断し、②配転命令権の濫用については、⑴業務上の必要性のない場合、⑵不当な動機や目的をもって配転命令権が行使された場合、⑶配転命令権の行使が労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等の特段の事情が認められる場合には、配転命令権の行使は権利の濫用として無効となると判断されています。
(3) 職種・勤務地限定合意について
使用者と労働者との間の労働契約によって職種や勤務地が限定されていると認められる場合(例えば契約上「●●以外の職種には従事させない」といった合意や「●●県以外では業務に従事させない」といった合意をしている場合)には、そもそも当該職種や勤務地以外での就労を内容とする配転を命じることはできません。
2 本判決について
(1) 本判決の事案の概要
本件は、使用者であるYが運営する高齢者や身体障害者に適合した福祉用具の普及を目的とする施設であり、施設内に展示室や福祉用具の改造・製作サービスを提供する工作室を備えているAに勤務する労働者Xの配転命令が問題となった事案です。
Xは、一般技能士、職業訓練指導員、ガス溶接作業主任者等の資格を保有していましたが、平成13年4月、Aの所長から、溶接ができる機械技術者を募集しているとの理由でAでの勤務勧誘を受け、同年4月1日から正規職員としてYに雇用されAにおいて、福祉用具の改造・製作、技術の開発などの業務(以下「本件業務」といいます。)を行う主任技術者として18年間勤務してきました。
平成23年度以降、Aにおける福祉用具の製作の実施件数は、次第に減少するようになりました。これを受けて、平成31年3月25日に人事異動の内示が発表され、Xは技術職から総務課に配転されることとなり、YはXに同年4月1日付けでの配転を命じました(本件配転命令)。
これに対して、Xは、Yに対して本件配転命令はXY間の職種限定合意に反するものであり違法であるとして損害賠償等を求めて裁判を提起しました。
一審(京都地裁令和4年4月27日判決・労働判例1308号20頁)及び控訴審(大阪高裁令和4年11月24日判決・労働判例1308号16頁)は、XY間に黙示の職種限定合意があると認めましたが、福祉用具の製作の実施件数の減少を踏まえ、Xの解雇を回避するためにはXを総務課に配転することも業務上の必要性があり、業務内容も不可として大きくなく、通常甘受すべき程度を超える不利益をXにもたらすものではないとして権利濫用を否定して、Xの請求を棄却しました。
これに対して、Xが上告をしたことで審理判断されたのが本裁判例となります。
(2) 本判決における主要な争点及び判断事項
- XY間の職種限定合意の有無
- 職種限定合意が認められる場合の配転命令権の存否
(3) 判決要旨
最高裁判所は、本件について以下のように判示し、職種限定合意が認められる場合には、使用者は労働者に対して、その個別の同意なしに配転を命じる権利がないとして、配転命令権があることを前提に権利濫用の有無について判断をした原審の判断に誤りがあるとしました。
|
労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上記事実関係等によれば、上告人(労働者X)と被上告人(使用者Y)との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。 そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 |
※上記枠内の括弧部分は当職による。
3 留意すべき事項について
本判決は、職種限定合意の存在を認定したうえで、本件が配転命令権の濫用の問題ではなく、配転命令権の有無の問題であることを判断しました。
労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた場合、使用者はその範囲を超える配転を命じることはできないということは学説上の定説でした。しかし、これまで最高裁判決においてこの点を明示したものはなく、職種限定合意がある場合には使用者は労働者に対し、その個別的同意なくして配転を命ずることはできないということを最高裁判所が明言した点において、本判決は重要な意義を持ちます。本判決の判示内容は、勤務地限定の合意の場合にも妥当するものと考えられます。
更に、ここで重要なのは、どのような場合に職種や勤務地を限定する合意があったと判断されるのかという点ですが、本事例では、Yの職種を本件業務に限るとの書面による合意(明示の合意)は認定されていません。しかし、原審及び第一審において、黙示の合意があるとして、比較的緩やかに職種限定合意を認定した印象を持ちました。
そのため、契約書に職種限定合意の文言が存在しないからといって安心してはならず、どのような事実によって黙示の合意が認定されるのかを正しく理解しておくことが重要となります。
この点について、本判決で最高裁判決では黙示の合意について具体的な認定をしていませんが、原審及び第一審は黙示の合意を認定しており、採用の経緯や長年の勤務実績等に照らして合意内容として機械技術者以外の職種に就かせることを想定していなかったとして当事者間の合理的意思を推認しております。そのため、職種限定合意の有無を判断するにあたっては、当該合意が労働契約等において明示されている場合の他は、企業の規模、組織、当該労働者の学歴、資格、採用方法、採用場所、どの程度配転の必要性のある事業形態であったか、配点についての従前の実績等の諸般の事情を総合考慮して当事者の合理的意思を検討される可能性がありますので、注意が必要となります。