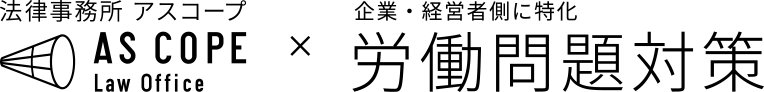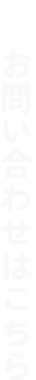労働災害発生時の会社の対応義務とは?リスクを最小化する初動と手続き

Q
自社で従業員が業務中に機械に手を挟まれ、怪我をしてしまいました。初めてのことで、何から手をつければ良いか分からず混乱しています。とりあえず救急車は呼びましたが、この後、会社として何をすべきなのでしょうか。行政への報告は必要ですか?労災保険の手続きを進めれば、会社の責任はそれで終わりになるのでしょうか。対応を誤ると、会社にどのようなリスクがあるのか、法的な観点から具体的に知りたいです。
自社で従業員が業務中に機械に手を挟まれ、怪我をしてしまいました。初めてのことで、何から手をつければ良いか分からず混乱しています。とりあえず救急車は呼びましたが、この後、会社として何をすべきなのでしょうか。行政への報告は必要ですか?労災保険の手続きを進めれば、会社の責任はそれで終わりになるのでしょうか。対応を誤ると、会社にどのようなリスクがあるのか、法的な観点から具体的に知りたいです。
労働災害が発生した場合、会社には法律上、複数の対応義務が課せられます。まず最優先すべきは被災労働者の救護と二次災害の防止です。その後、労働基準監督署長への「労働者死傷病報告」の提出義務、労災保険給付手続きへの協力義務を誠実に履行せねばなりません。仮に労災保険が適用されても、会社の「安全配慮義務」違反が問われれば、民事上の損害賠償責任を別途負う可能性があります。これらの対応義務を怠ると、刑事罰や多額の賠償金、会社の社会的信用の失墜といった深刻なリスクに繋がるため、迅速かつ適切な対応が不可欠です。
ポイント
- ・被災労働者の救護と二次災害の防止を徹底し、会社の損害拡大を食い止める。
- ・労働者死傷病報告を法定通りに行い、「労災隠し」による刑事罰のリスクを回避する。
- ・労災保険手続きに誠実に協力し、従業員との無用な紛争を未然に防ぐ。
- ・平時から安全配慮義務を履行する体制を構築し、有事の際の民事賠償リスクに備える。
目次
1. 労働災害発生直後、会社が最優先で果たすべき初動の対応義務
万が一、事業場で労働災害が発生した場合、経営者や管理者がパニックに陥ってしまうケースは少なくありません。しかし、このような緊急時こそ、冷静かつ的確な初期対応が会社のダメージを最小限に抑える鍵となります。
会社が法的に、そして社会的な責任として真っ先に果たすべきは、被災した労働者の救護ですが、その後、二次災害の防止対策を講じることも極めて重要です。例えば、機械の緊急停止、危険区域への立ち入り禁止措置、他の作業員への注意喚起などを速やかに行い、被害の拡大を防ぐ必要があります。このような初動対応を怠った場合、被害が拡大し、会社の安全配慮義務違反が問われる事態になりかねません。
また、事故原因を正確に究明するため、事故現場の保存も重要です。例えば、写真や動画で記録を残しておくことは、後の原因究明や行政への報告、万一の訴訟に備える上で有効な手段となります。
これらの初動対応は、単なる事後処理であるにとどまらず、会社に危機管理能力が備わっていることの表れとして重要であるといえます。
2. 行政への報告義務違反のリスク-「労働者死傷病報告」の実務
労働災害が発生し、労働者がこれにより死亡または休業した場合には、会社は所轄の労働基準監督署長に対して「労働者死傷病報告書」を提出する労働安全衛生法上の義務を負っています。この報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりする、いわゆる「労災隠し」は重大な法令違反であり、「労災隠し」がなされたと認定されると、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるのみならず、会社の社会的信用が失われる可能性がございます。
労働者死傷病報告書は、対象労働者の休業が4日以上に及ぶ場合は、遅滞なく提出しなければなりません。一方で、休業日数が4日未満の比較的軽微な災害であっても、四半期ごとにまとめて報告する義務があります。報告書のひな形は厚生労働省のホームページに掲載されていますが、記載方法が分からない場合には弁護士や社労士に相談することを推奨します。
労働災害は起こり得るものという前提に立ち、発生した際には誠実かつ迅速に法的手続きに則って報告することが、最終的に会社を守ることに繋がります。
3. 労災保険の手続きにおける会社の協力義務とその注意点
労働者が労働災害により負傷した場合、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく給付を受けるために、様々な請求手続きが必要となります。この手続きにおいて、会社は従業員に対して誠実に協力する義務があります。特に重要であるものが、療養(補償)等給付請求書(通称:様式第5号や第16号の3など)において記載が求められる**「事業主証明」**です。
この証明は、災害の発生日時や状況について、事業主が記載内容の通りであったことを証明するものです。この証明があることで、労働基準監督署は迅速に保険給付の判断を下すことができます。
実務上、会社側が「これは業務中の災害とは認められない」と考え、事業主証明を拒否するケースが多々見られます。しかし、事業主証明はあくまで労働者の申告内容を会社として把握していることを示すものであり、会社が災害の法的責任を認めるということにはなりません。また、労災保険法施行規則上、会社は正当な理由がない限り労災の事業主証明を拒否することができないとされています。安易に証明を拒否すると、被災した従業員との関係が悪化し、不要な紛争を招く一因となるのみならず、上記の「労災隠し」が疑われるリスクも生じます。もしも災害の発生状況等に疑義がある場合は、証明欄の横に会社の見解を付記(意見の申出)することも可能です。従業員との信頼関係を損なわず、円滑に手続きを進めるためにも、まずは誠実な協力姿勢を示すことが重要です。
4. 労災保険だけでは終わらない「安全配慮義務」と損害賠償リスク
労災保険は、被災労働者の治療費や休業中の所得を補償するものであり、精神的苦痛に対する慰謝料は含まれていません。また、逸失利益(後遺障害によって将来得られなくなる収入)についても、必ずしも全額が補填されるわけではありません。
会社は、労働契約法第5条に基づき、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする「安全配慮義務」を負っています。労働災害の発生原因が、この安全配慮義務違反(例:危険な機械の安全装置が未設置だった、十分な安全教育を行っていなかった等)にあると裁判所が判断した場合、会社は労災保険給付とは別に、被災労働者に対して民事上の損害賠償責任**を負うことになります。
この損害賠償額は、慰謝料や逸失利益の不足分などを含めると、数千万円から時には億単位に上ることもあり、会社の財務に深刻な打撃を与えかねません。労災保険の適用は、あくまで最低限の補償であり、会社の民事責任を免除するものではないという点を、経営者は常に認識しておく必要があります。
5. 将来の紛争を防ぐための再発防止策と安全衛生管理体制の構築
労働災害が発生してしまった場合、事後対応を適切に行うことはもちろん重要ですが、それ以上に重要であることは**「なぜ災害が起きたのか」を徹底的に究明し、実効性のある再発防止策を講じること**です。これは、他の従業員を同様の危険から守るという会社の責任を果たすと共に、将来的な労働災害リスク、ひいては経営リスクそのものを低減させるために不可欠です。
具体的な原因究明にあたっては、現場の状況、作業手順、管理体制、機械設備の問題点など、多角的な視点から分析する必要があります。そして、その結果に基づき、「作業手順書を改訂する」「危険箇所に物理的な防護柵を設置する」「安全に関する研修を定期的に実施する」といった具体的な再発防止策を策定し、全社的に徹底させなければなりません。
特に、常時使用する労働者が50人以上の事業場では、業種に応じて「安全衛生委員会」の設置が義務付けられています。このような委員会を形骸化させず、労使が一体となって職場の危険性について調査審議し、経営層に提言する場として機能させることが、継続的な安全衛生管理体制の構築に繋がります。平時からの地道な取り組みこそが、有事の際に会社と従業員を守る最大の防御策となるのです。