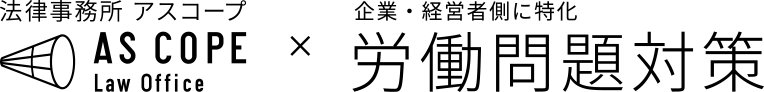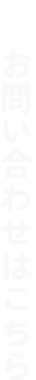休職命令から自然退職までの注意点

目次
【本稿は2024年10月号のニュースレターにて執筆されたものです】
ASCOPEでは企業活動に関わる法改正や制度の変更等、毎月耳よりの情報をニュースレターの形で顧問先の皆様にお届けしております。
会社法務に精通した社会保険労務士、顧問弁護士をお探しの企業様は、是非ASCOPEにご依頼ください。
メンタルヘルス不調その他の傷病を抱えた従業員がいる場合、会社としては、安全配慮義務に基づき適切な対応を取る必要がある一方、業務に支障が出ており、当該従業員を辞めさせたいと考えることもあるでしょう。そのような場合に、休職命令を出し、休職期間満了日までに治癒しなかったことをもって自然退職扱いとする方法が考えられます。
本NewsLetterでは、休職命令発令後、自然退職までの流れにおいて、会社として注意すべき点についてご説明させていただきます。
第1 休職制度と解雇について
そもそも、休職制度は、労働者が私傷病によって労働契約の債務の本旨に従った労務の提供が不可能若しくは著しく困難となった場合に、当該労働者との労働契約自体は維持しつつも、当該労働者の労務の提供を免除する措置であり、労働者保護のための解雇猶予制度であると理解されています(エール・フランス事件・東京地裁昭和59年1月27日判決)。
したがって、就業規則に休職の規定が存在するにもかかわらず、休職を経ずに、私傷病それ病自体や休職命令を拒否したことを理由に解雇すると、解雇権の濫用と判断される可能性が高いと考えられます。
よって、解雇を検討するような状況である場合も、休職期間を経たとしても正常な労務提供が到底不可能であることが医学的に判断されるような特別の事情がない限り、まずは休職命令を出すことが安全であるといえます。
なお、休職制度は、就業規則等の定めに基づく制度ですので、就業規則等に定めがなかったり、適切な内容の定めになっていなかったりする場合には、休職命令が無効となったり、休職期間満了による自然退職が認められなかったりすることもあることにご注意ください。
第2 休職事由の検討について
1 退職事由となりうるかという観点
休職期間の満了により自然退職の効果が生じるため、原則として、休職命令の直接の事由となった傷病と、休職期間満了時において労務提供を困難とする事情とは、別の事情によるものであってはいけません(シャープNECディスプレイソリューションズ事件・横浜地裁令和3年12月23日判決)。
つまり、会社としては、後の休職期間満了時に労務提供を困難とする事情となりうる事情が複数存在する場合、それら一つひとつが今後業務遂行にどのような影響を与えうるか、休職命令発令前に調査しておく必要がございます。
具体的には、就業規則の定めによるものの、以下の方法が考えられます。
|
①休職期間満了時に労務提供を困難とする事情となりうる事情について、何らの診断もなされていない場合 ➡まずは受診命令を発令し、診断書の提出を求めます。また、症状の程度によっては、同時に自宅待機命令(会社の命令での待機である以上、給与の支払が発生します。)を発令します。提出された診断書に疑義がある場合、会社が指定する別の医師への受診命令を出し、また、必要に応じて、当該診断書を作成した医師との面談を求めます。 なお、個人情報保護の観点から、医師との面談は、本人の同意を得た上で行うべきです。 ②休職期間満了時に労務提供を困難とする事情となりうる事情について、本人が診断書を提出した場合 ➡特に、メンタルヘルス不調のケースで、本人が選択した精神科(主治医)を受診して診断書を提出してきたような場合は、主治医が会社の安全配慮よりも患者との信頼関係を重視した結果、本人の意見に沿った診断書が作成されている可能性がございます。そこで、本人の健康状態を正確・公平に把握するために、会社が指定する指定医(会社における業務態様を把握し、労働安全衛生法に従って助言できる産業医等が望ましい)への受診も命じます。 また、主治医面談も同様に有効です。 |
以上のような方法で得られた診断書や意見書、主治医面談の結果を踏まえ、労務提供を困難とする事情となりうるかという観点で業務遂行への影響を十分に検討した上で、その後の対応を決定することが重要です。
2 労働基準法19条1項との関係
労働者の傷病が業務に起因するものである場合、休業期間中及び治癒後30日間は解雇が禁止されています(労働基準法19条1項)。
休職期間満了日までに傷病が治癒しなかったことをもって自然退職とする場合には、解雇とは異なりますが、裁判実務においては、休職事由となった傷病に業務起因性が認められる場合は、労働基準法19条1項が類推適用され、自然退職扱いは無効であると解されています(東京地裁令和5年12月7日判決、大阪高裁平成24年12月13日判決、大阪高裁令和2年11月13日判決等。)。
そこで、休職事由の検討においては、当該事由が業務に起因するものでないか、本人のみならず(プライバシーに配慮しつつ)関係従業員への聞き取りを行う等により、慎重に調査・検討する必要がございます。
第3 休職期間中の対応について
1 会社による健康確認
休職とは、当該期間休むことを保証する制度ではなく、就労義務を免除して療養に専念させる制度であり、従業員は職務に復帰できるように傷病の療養に専念する義務(療養専念義務)を負っていると考えることができます(もっとも、療養専念義務について就業規則上に明記しておく方がよいでしょう。)。したがって、会社としては、療養継続が必要か否かを適時に確認することが重要です。
そのための方法として、診断書の提出等による報告を定期的に求めることが有効です(その旨も就業規則に定めておくことが望ましいところです。)。
報告の頻度は1~3か月に1回程度とし、場合によっては、人事や上司のようにプレッシャーのかかる相手ではなく、産業保健スタッフや産業医、家族等を通じた連絡体制を構築することが適切です。
2 療養専念義務違反への対応
例えば、休職中にもかかわらず、SNSの投稿等で療養専念義務に反すると思われる行為が発覚した場合は、会社側専門医とともに医学的にみて当該行為が不適切かどうか検討します。
療養に専念していないことが医学的に明らかであれば、これを理由として、服務規律違反として厳重注意や指導を行うことが考えられます。
さらに、上記検討の結果、当該行為が医学的にみて療養の趣旨に反するといえるのみならず、注意指導にも従わないような場合には、譴責等の軽いものから懲戒処分を行っていくことも考えられます。
第4 休職事由の消滅(=治癒)の判断について(裁判例の傾向)
1 原則
原則として、休職を経て治癒したといえる状態とは、労働契約における「債務の本旨に従った弁済」(民法493条)が行える状態、すなわち、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復した状態を指すと解されます(昭和電工事件・千葉地裁昭和60年5月31日)。
よって、休職期間を延長したとしても従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復する見込みがない場合には、期間満了退職扱いすることとなります。
2 例外
⑴ 休職直前の業務が軽減業務であった場合
上記原則を前提としつつ、裁判例では、休職前の業務が極めて軽微であった場合について、休職前に業務を軽減したか否かにより復職判断の基準が変わってしまうことの不均衡・不公平から、復職の可否を判断するにあたって前提とすべき「業務」とは、対象者が休職前に実際に担当していた業務ではなく、本来行うべき職務を基準とすべきと判断されています(独立行政法人N事件・東京地裁平成16年3月26日判決)。
⑵ 職種・職務限定合意がない場合
また、職種・職務限定合意がない場合については、休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、使用者の規模や業種、その社員の配置や異動の実情、難易等を考慮して、配置替え等により現実に配置可能な業務の有無を検討すべきとされています(JR東海事件・大阪地裁平成11年10月4日判決)。
⑶ 職種・職務限定合意がある場合
さらに、職種・職務限定合意がある場合については、直ちに従前業務に復帰できない場合でも、比較的短期間で復帰することが可能である場合には、休業又は休職に至る事情、使用者の規模、業種、労働者の配置等の実情からみて、短期間の復帰準備時間を提供したり、教育的措置をとることが信義則上求められるとされています(全日本空輸事件・大阪高裁平成13年3月14日判決)。
また、労働者の職種がトラック運転手に限定されていた事案において、他に現実に配置可能な部署ないし担当できる業務が存在し、会社の経緯上もその業務を担当させることにそれほど問題がないときは、債務の本旨に従った履行の提供ができない状況にあるとはいえないと判断されています(カントラ事件・大阪高判平成14年6月19日判決)。
3 小括
このように、原則として「治癒」とは限定された職種を従前どおりに遂行できることを意味しますが、裁判例の傾向からすれば、これは一切の例外を許さないというものではないものと考えられます。
やはり、私傷病による即時普通解雇の場合に解雇権濫用法理により厳格な合理性審査を受けることとの均衡からして、復職の見込みがないことの判断については厳格な判断が要求される傾向にあるといえます。
そこで、会社としては、復職の見込みがないと判断するにあたっては、上記裁判例の判断方法を踏まえつつ、今後短期間では復帰見込みがないことに関する医学的証拠(主治医の診断書に加え、産業医の意見書。また、メンタルヘルス不調の場合には、内科医でなく精神科の意見書。)を適切に整えておくことが必要です。
第5 最後に
傷病を抱えていると疑われる従業員への対応についてご不明な点がある場合や、休職命令を出すことをご検討の場合には、是非担当弁護士にご相談いただけますと幸いです。