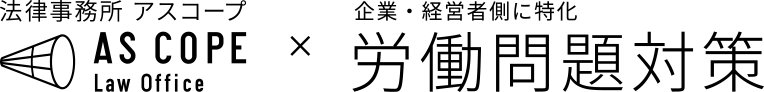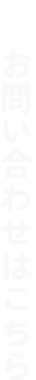ハラスメント調査委員会の設置・運営|企業が知るべき法的リスクと実務

Q
従業員から「上司からパワハラを受けている」との深刻な相談がありました。社内で調査を進めたいのですが、誰が担当すればよいのか、また、どのような手順で進めればよいのか分からず困っています。当事者の一方から「会社は信用できない」と言われかねず、調査の公平性・中立性をどう担保すればよいのでしょうか。調査委員会を設置すべきという話も聞きますが、 中小企業で、どのように設置・運営すればよいのか、具体的な方法と法的な注意点を教えてください。
従業員から「上司からパワハラを受けている」との深刻な相談がありました。社内で調査を進めたいのですが、誰が担当すればよいのか、また、どのような手順で進めればよいのか分からず困っています。当事者の一方から「会社は信用できない」と言われかねず、調査の公平性・中立性をどう担保すればよいのでしょうか。調査委員会を設置すべきという話も聞きますが、 中小企業で、どのように設置・運営すればよいのか、具体的な方法と法的な注意点を教えてください。
ハラスメントの申告を受けた場合、原則、企業は当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の措置を講じなければならない義務を負います。調査の客観性・中立性を担保するため、「ハラスメント調査委員会」の設置は極めて有効な手段です。ただし、委員会のメンバー構成や調査手順を誤ると、調査そのものが無効と判断されたり、新たな紛争の火種となったりするリスクがあります。本コラムでは、企業規模に応じた現実的な調査委員会の設置方法、中立性を確保するための具体的なポイント、そして調査結果の適切な取り扱いについて、企業側の弁護士の視点から解説します。
ポイント
- ・企業の法的義務であるハラスメント調査の重要性とリスクを理解する。
- ・調査委員会の「中立性」を確保するための具体的なメンバー選定方法を学ぶ。
- ・調査プロセスで必須となるプライバシー保護と不利益取扱いの禁止を徹底する。
- ・調査報告に基づき、法的に妥当な懲戒処分を判断するための基準を把握する。
- ・二次ハラスメントや紛争拡大を防ぐための報告・フォローアップ体制を構築する。
目次
1. なぜハラスメント調査委員会が必要か?企業の法的義務と怠るリスク
従業員からハラスメントの申告を受けた際、企業は労働施策総合推進法第30条の2に基づき、雇用管理上の措置義務を負います。その中核となるのが「事実関係の迅速かつ正確な確認」です。この調査義務を怠ったり、不適切な調査を行ったりした場合、企業は安全配慮義務違反(労働契約法第5条)を問われ、被害者から損害賠償を請求されるリスクに直面します。
調査を特定の担当者一人に任せると、どうしても個人的な関係性や憶測が入り込む余地が生まれ、「調査が不公平だ」という新たな不満を生み出す原因になりかねません。そこで有効となるのが、複数名で構成される「調査委員会」の設置です。
調査委員会を設置する最大の目的は、調査の客観性、中立性、専門性を担保することにあります。組織として正式な機関を立ち上げて調査に臨む姿勢を示すことは、申告者・被申告者の双方に対して「会社は真摯に対応している」というメッセージとなり、調査への協力を得やすくなる効果も期待できます。逆に、調査体制が不十分であると、後の労働審判や訴訟において「企業の調査は信用できない」と判断され、企業にとって著しく不利な状況を招くことになります。
2. 実効性のあるハラスメント調査委員会のメンバー構成と「中立性」の確保
ハラスメント調査委員会の生命線は、その「中立性」にあります。委員会の構成メンバーが、申告者または被申告者のいずれかと極端に近い関係にあると、調査結果の信頼性が根本から揺らぎます。
委員会の構成メンバーは、一般的に3名から5名程度の奇数で構成することが望ましいとされます。メンバー選定にあたっては、以下の点を考慮する必要があります。
内部委員の選定:人事・労務部門の責任者や法務部門の担当者は、社内規程や労働法規に精通しているため、中心的な役割を担うことが期待されます。加えて、当該事案と直接利害関係のない他部署の管理職をメンバーに加えることで、組織内の多様な視点を取り入れ、客観性を高めることができます。社長や担当役員が直接委員となることは、事案の重大性によっては考えられますが、予断を与えかねないため、慎重な判断が必要です。
外部専門家の活用:事案が複雑・重大である場合や、社内だけでの中立性確保が難しい場合には、外部の弁護士や社会保険労務士を委員として招聘することを強く推奨します。外部専門家が加わることで、法的な観点からの的確な助言が得られるだけでなく、調査の独立性が内外に示され、調査結果の信頼性が格段に向上します。特に、企業側の労働問題を専門とする弁護士は、紛争化した場合のリスクを見据えた調査の進め方について、実践的な助言が可能です。
企業の規模によっては、毎回外部専門家を入れることが現実的でない場合もあるでしょう。しかし、少なくとも顧問弁護士等に調査プロセスの妥当性について助言を求めることは、リスク管理の観点から不可欠と言えます。
3. ハラスメント調査の具体的な進め方と法務上の注意点
調査委員会を設置したら、具体的な調査計画を策定し、迅速に実行に移します。調査のプロセスにおいては、特に以下の点に法務上の注意が必要です。
まず、調査の基本は関係者からのヒアリングです。対象は、①申告者、②被申告者、そして③目撃者や周辺の同僚などの第三者です。ヒアリングは、プライバシーが確保された静かな会議室などで行い、高圧的になったり、誘導的な質問をしたりすることは厳に慎まなければなりません。ヒアリングの冒頭では、調査の目的、プライバシー保護の徹底、調査に協力したことによる不利益な取り扱い(解雇、降格、異動など)は絶対にしないことを明確に約束します。これは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、パワハラ防止指針でも事業主の義務として定められている事項です。
ヒアリング内容は、後日の証拠となるよう、日時、場所、同席者、質問事項、回答内容を詳細に記録します。可能であれば、対象者の了承を得て録音することも有効ですが、無断録音は新たなトラブルの原因となるため避けるべきです。
また、調査の過程で得られた情報は、個人情報保護法の観点からも厳重に管理しなければなりません。調査関係者には守秘義務を課し、情報が不必要に拡散しないよう徹底した管理が求められます。こうした手続きの一つ一つを丁寧に行うことが、調査の正当性を担保し、企業を守ることにつながります。
4. 調査結果の取り扱いと懲戒処分における判断のポイント
すべての調査が完了したら、調査委員会は収集した事実や証拠を基に、ハラスメントの有無を認定し、調査報告書としてまとめます。
この報告書には、客観的な事実認定と、それに基づく委員会の結論を明確に記載する必要があります。「パワハラがあったように思われる」といった曖昧な表現ではなく、「いつ、どこで、誰が、誰に対し、どのような言動を行い、その言動は就業規則第〇条に定めるパワーハラスメントに該当する」というように、具体的に記述することが重要です。
ハラスメントの事実が認定された場合、次に行うのが行為者に対する処分(人事権・懲戒権)の検討です。特に、注意すべきは、懲戒処分における「処分の相当性」です。過去の裁判例では、ハラスメント行為の内容・態様、被害の程度、行為者の役職や過去の懲戒歴、反省の態度などを総合的に考慮して、処分の重さが判断されます。例えば、一度の注意指導だけでいきなり懲戒解雇とするのは「懲戒権の濫用」(労働契約法第15条)と判断され、無効となる可能性が極めて高いでしょう。
調査委員会は、懲戒処分の種類(譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇など)について、就業規則の規定と事案の重大性を照らし合わせ、相当と考えられる処分案を経営陣に答申する役割も担います。最終的な決定は経営の専権事項ですが、調査委員会の客観的な意見は、その判断の正当性を裏付ける重要な根拠となります。